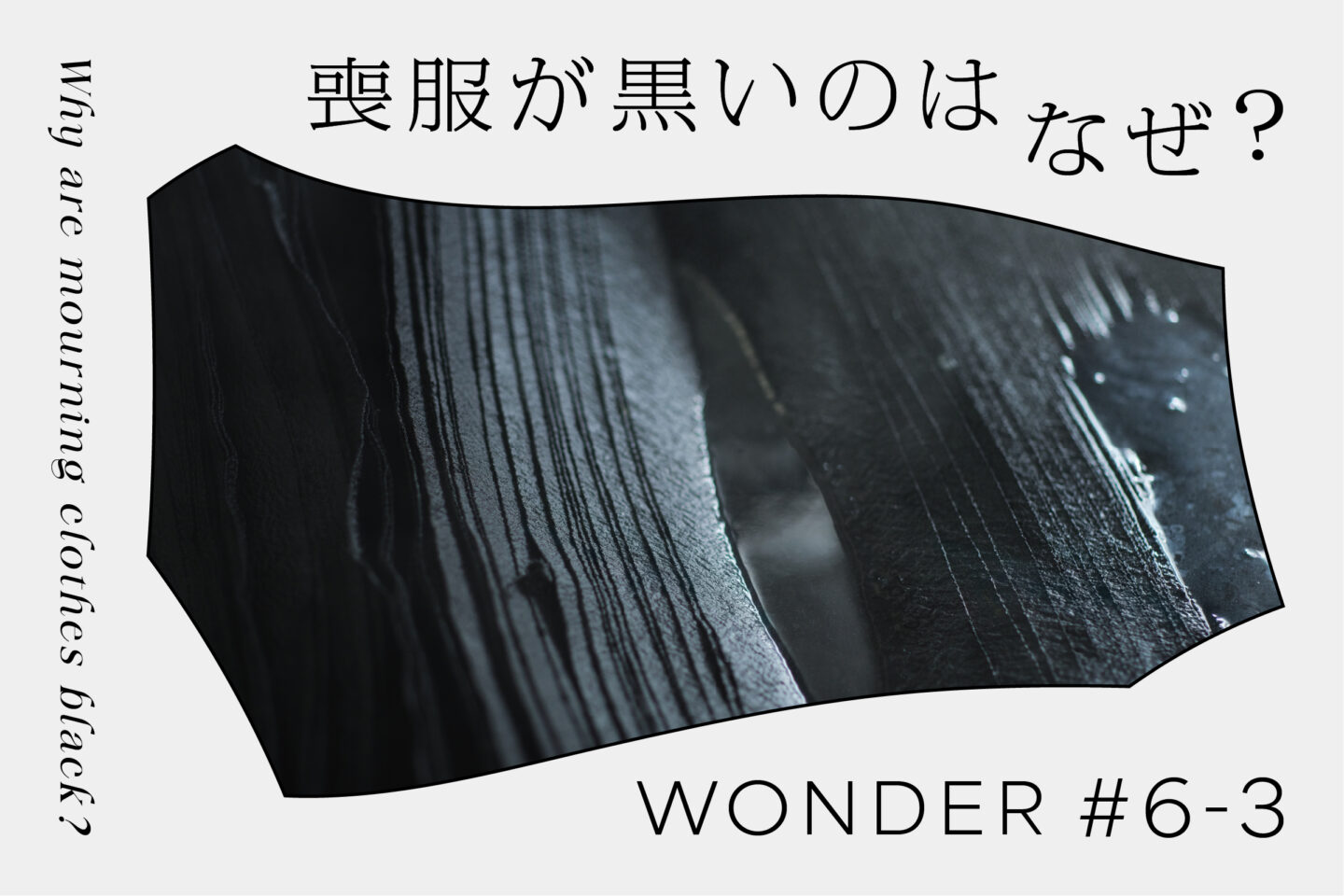
喪服が黒いのはなぜ?|後編
喪服はどうして黒いのか、深い黒は一体どのようにして生まれるのか? 喪服の「黒」を探求すべく訪れたのは、京都・壬生に本社を構える『株式会社京都紋付』。日本の伝統的な正装である「黒紋付」を100年以上染め続けてきた老舗企業だ。先代の荒川忠夫が残した「身体を切ったら、黒い血が出てくるかもしれん」という言葉通り「黒」だけにこだわり、現在でも長年の経験により築かれた独自の技術を用いて深みのある美しい黒を追求し続けている。
今回は『株式会社京都紋付』三代目代表の荒川徹さんに、同社の代名詞ともいえる「黒紋付」が持つ文化的背景から日本人と黒の関係性まで、お話をうかがった。


黒紋付の広まりと、長い歴史のなかで追い求めるもの
「黒紋付」とは黒無地の着物の背中、両袖、両胸の計5箇所に家紋を染め抜いた、日本の正式な礼装。いまでも主に喪服や礼服として用いられる黒紋付だが、産業としていつ発展し、日本の暮らしに根付いていったのだろうか? その背景には、染色技術の大きな変化があった。
黒紋付というと、いまでは冠婚葬祭などで着用する「第一礼装」ですが、歴史をたどると、もともとは江戸時代(17世紀初頭)から武士の間で愛用されるものでした。当時は家紋というのも武士の身分を表す象徴で、着ることを許されていたのは上流の人々だけだったんですね。それが明治時代に入ると一般の人でも家紋を纏うことが許されるようになり、黒紋付は庶民の間にも徐々に広がっていきます。ただ、明治時代の紋付はいまのような深い黒ではなく、草木を加工した自然染料で染められていたので、薄墨色と呼ばれるようなグレーに近い色でした。
そこに大きな変化が訪れたのが、大正時代。化学染料が普及し、反物を深い黒に染め上げる技術が生まれます。さらに染料を継ぎ足しながら反物を連続して染められる技術が開発され、大量生産が可能になったことで、黒紋付は大衆に馴染んでいったというのが、大きな流れです。(荒川)


↑黒紋付製造は、分業によって行われる。左は家紋部分を染め抜くために防染糊を置く職人。糊を作る工程から自ら行うが、国内に残る紋糊置き職人はわずか2名とのこと。右は糊置きされた反物を黒染めし、紋糊を落とす工程までを行う職人。染料に浸ける前工程では、ずらりと並んだ細い針に素早い手つきで反物を掛けていく。
『京都紋付』の創業は大正4年(1915年)、日本の黒染めに革新的な変化が起こった時代の真っ只中に誕生した。のちに100年の時をかけ、黒紋付染という伝統産業を現代へと継承していく存在となるのだが、『京都紋付』は大正、明治、昭和、平成、そして令和という時間のなかで、ただひたすらに奥行きのある黒に美しさを見出し、その深みを追い求め続けている。
まず黒紋付というのは柄がなく、価値を表現するものは「家紋」と「黒」、この2つだけなんです。創業者であるおじいさんは分業制で成り立つ着物業界の中で、柄物ではなく無地物、そのなかでも「黒専門の染め屋」という道を選び、黒一色に全身全霊を込めてきました。深みのある黒を出すために何度も下染めを繰り返し、染料の温度を微妙に変化させながら多くの手間をかけて美しい黒を追い求めてきました。他に黒染めに欠かせないのが、良質な水。京都には琵琶湖よりも多くの水が溜まっていると言われており、特に我々が本社を構える壬生は良質な地下水が湧くので、質の高い黒染めを行うために染色の全行程に壬生の地下水を使用し続けています。
我々がつくり出したいのは、実質的な「黒さ」だけでなく、袖を通したときに背筋が正されたり、自分を律するような気持ちそのもの。そういった黒の不思議な力は、文化ともいえるものだと思うんです。(荒川)

京都紋付が実現する革新的な「黒」
丁寧な染色工程、良質な水を使って美しい黒を追い求めてきた『京都紋付』だが、その長い歴史のなかで独自の進化を遂げ、世界でも類を見ない究極の黒を実現させる「深黒(しんくろ)加工」という技術をいまから40年ほど前に確立させている。
一度黒染めを施した反物に対し、さらに独自の「黒をより黒くする加工」を行い染め上げられた紋付は、文字通り「深黒」と呼ぶにふさわしい、奥行きを帯びた仕上がりとなる。
「深黒加工」は、通常の黒染めを施したあと、光を吸収する特殊な薬品を生地に染み込ませるといった再加工を行うことで、視覚的により黒く見せる技術なんです。単に色を重ねるのではなく、光の吸収率を高めるというアプローチで、世界一黒い塗料とも言われる「ベンタブラック」の構造にも通ずるものがある。光の吸収率を上げる=光が見る人に届かないという原理の究極でいえば、ブラックホールですよね。
実は深黒加工に使用される薬品自体は黒ではなく乳白色で、生地に含浸させることで凹凸が目立たなくなり、布が平面的に見えるほどの深黒を実現します。例えば赤・白・黒のボーダーTシャツに加工を施したとき、赤と白はそのままで、黒の部分だけが一段と深く沈んだ黒になるという実証実験の結果があるのですが、それを想像してもらうと、黒という色をつけて加工しているわけではないということがわかりやすいかと思います。
まずはビーカーで薬品を試験し、次にラインでテストを行う。その過程で「継続性」や「安定性」を確認します。でも、完璧だと思っても予想外の結果になったり、経年変化で問題が出たりして、一筋縄ではいかない。開発に5年、仕上がりに自信を持てるまでには最終的に10年かかりました。(荒川)
「深黒加工」は、ただ黒い染料を重ねていく従来の手法とは異なり、「光の吸収によって黒くみせる」という人間の視覚を利用した革新的な技術。光吸収率の高さでより深い黒を実現する仕組みは、WONDER#2のテーマであった「光と闇」を彷彿とさせ、同回の後編で取材をさせていただいた『暗素研』で開発される製品の理論ともどこかつながりを感じる。『京都紋付』が染める黒紋付の奥行きのある黒が、染色による「色としての黒」だけでなく、目に光が入らない状態=「闇としての黒」という科学的な視点からも成り立っていたことは、正直なところ驚きである。


喪服はなぜ黒い?
いよいよ今回のテーマ「喪服ってどうして黒いの?」について、疑問を投げかけてみた。中編のアンケートでは、多くの人が当たり前の慣習として受け入れたうえで、自分や場への向き合い方、在りたい姿を黒に重ねる回答が多数見受けられたが……喪服としても着用される黒紋付と長年向き合い続けてきた荒川さんは、どう考えられているのだろうか。
日本人にとって黒とは「自分を控える」「身を慎む」という意味を持つ色だと思うんです。喪服として黒を纏うことで、自分の存在を控えて、故人を静かに偲ぶ。また、日本語には黒を表す表現がたくさんありますよね。漆黒、カラスの濡羽色、檳榔子黒(びんろうじぐろ)……英語なら「ブラック」と「ダーク」くらい。
日本人の黒い瞳は「黒」を敏感に感じられると言われていて、特に黒に対して感度が高く、豊かな感覚を持ってきた民族だと思っています。イタリアのように鮮やかな色彩を好む文化もありますが、日本は昔から「陰影」の文化。障子越しに差し込む木漏れ日、ろうそくの灯りがつくる影、そうしたものの美しさを大切にしてきたと思います。黒は光を受け止めず、影の奥に静かに佇む色。だからこそ、日本人にとって黒は「控える」「慎む」という意味合いと強く結びついているのではないでしょうか。(荒川)
日本の伝統文化を守り続けている荒川さんらしいお答え。一方で、西洋からブラックフォーマルの文化が流入してきたこと、さらには明治時代に政府が、背中、両袖、両胸の五箇所に家紋を染め抜いた黒紋付を「第一礼装」として定めたことも、大きな転換点になったのだとも教えてくれた。静けさと慎ましさを感じさせる黒という日本古来の感性と、西洋の礼装文化が融合し、現在の喪服として「黒」が定着した、ということなのだろう。

黒紋付のこれまでとこれから
黒紋付が普及した流れの一つとして、嫁入り前の女性に、喪服を嫁ぎ先で新調するのは失礼だということで、家から送り出す際に黒紋付を持たせるという習慣がありました。それによって、当時は(女性)成人人口分と同じ数の黒紋付が毎年動いていたんですね。
ただ、昭和50〜60年ごろからはその習慣も廃れ、お葬式も「家で」「正装で」が基本だった時代から、場はセレモニーホールへと移行し、略礼服が一般的になっていきました。いま大半の人が着用している洋装のブラックフォーマルが略礼服だとご存知の方が一体どのくらいいるのかわかりませんが……。西洋の映画などに登場する、お葬式に参列する人々が黒い手袋とベールを纏う姿が、洋装における本来の正装。和装に置き換えると、五つ紋付きの黒紋付が本来の正装で、一つ紋付の羽織(背中に一つ家紋が入っている)というものが、略礼服にあたります。本来、喪主側がもっとも格式高い装いで弔問客を迎えるべきものですが、いまではその意識も薄れつつある。弔問客側が着用するものとされる、かつての一つ紋付羽織も忘れられていきました。
喪服という文化のかたちが崩れていくのは、日本の大切な通過儀礼がひとつ消えてしまうということでもあるのかなと。(荒川)

昭和の時代まで人々の身近にあった黒紋付も、時代の流れとともに徐々に姿を消している。しかし、装いが変化し、かつての形式が失われつつあるいまだからこそ、継承してきた伝統の価値を再発見することが求められているのだと荒川さんは語る。時代の転換期において『京都紋付』では、長い歴史のなかで得てきた「黒染め」の技術を、ただ守るだけではなく、次代へとつなげる新たなアプローチを模索している。
僕たちは、黒専門の染め物屋として“より黒く、美しく、色落ちしない黒”を追求してきました。黒紋付には柄がないからこそ、「黒の深さ」が製品の命となるんです。そこで長い年月をかけて培ってきた「深黒加工」や、染色が困難なシルクの紋付を染め上げてきた技術を生かして、汚れや色褪せで着用できなくなった衣類や、アパレルメーカーの不良在庫などを独自の染色加工で深みのある黒へと染め替える、新たな事業を展開しています。
これからは未来に向けて、黒染めという我々の持てる技術を、世界に発信したい。水質や流通など、解決が必要な問題はまだありますが、今後解決していくことは可能です。また、百貨店やアパレルブランドと協業し、廃棄衣類を新たな価値を持つ製品として再生させようという我々の取り組みや、黒に宿る日本独自の美意識を高く評価する海外の方は少なくないんです。
黒紋付染がたとえどれだけ衰退しても、新たな発信の仕方を見つけ、いまの世の中に必要なかたちに変えて、黒染めの伝統を後世に残していくこと。これが僕の使命だと思っています。(荒川)

喪服における「黒」に宿る、日本の精神性
喪に服すことと深い黒の関係性を辿っていくことで、黒という色が「色」の枠を超え、
日本人の美意識や死生観とも深い結びつきがあることが見えてきた。
黒は、陰影の奥に静かに佇む色だからこそ、故人や葬儀という場に向ける感情と、深く結びつく。
「僕にとって黒とは、人生そのものです。黒染めはある種、自己表現だとも思っているくらい。
僕の親父も“自分には黒い血が流れていると思う”という言葉を残していますが、僕も同じような感覚でいます」
そう語ってくれた荒川さんは、未来に向け、日本が誇る黒という文化を世界へ届けようと、日々邁進する。
静けさを纏う「深黒」は、新たなかたちで受け継がれ、これからの時代へと広がろうとしている。

荒川徹
1958年10月10日、京都府生まれ。1981年に甲南大学を卒業後、シライ電子工業株式会社に入社。1983年に株式会社京都紋付へ入社し、1996年より株式会社京都紋付および有限会社キョウモンの代表取締役社長を務める。2001年には京都黒染工業協同組合の理事に、2022年には一般社団法人テキスタイルアップサイクルプラットホームの理事に就任。現在も「黒一筋」の信念を胸に、黒染め文化の継承と革新に取り組んでいる。趣味はサッカー。

村木小百合
「黒の研究所」研究所員
SNS 担当。黒い物の写真を撮り、instagramに投稿することがライフワーク。子供のころから、洋服を作るのが好きで、専門学校卒業後、2004年にフォーマルウェアのリーディングカンパニーである株式会社東京ソワールにパタンナーとして入社。黒の色の違いを見分ける審美眼を養う。2児の母。趣味は旅行と、美術館巡り。