2025年、1月。
僕のスマホに、いつものように表示されたニュースには「デヴィッド・リンチ監督死去」の一行。
デヴィッド・リンチって、もはや生きていてもそこに存在しないというか、違う次元にいるような人。2017年に映画監督からの引退宣言をする前から新作映画を発表していないということもあって、 “時の人” のようなイメージで、自分と同じ時代を生きていないように感じられる方もいるでしょうし。そのくらい現実味がなかったような人だと思っています。
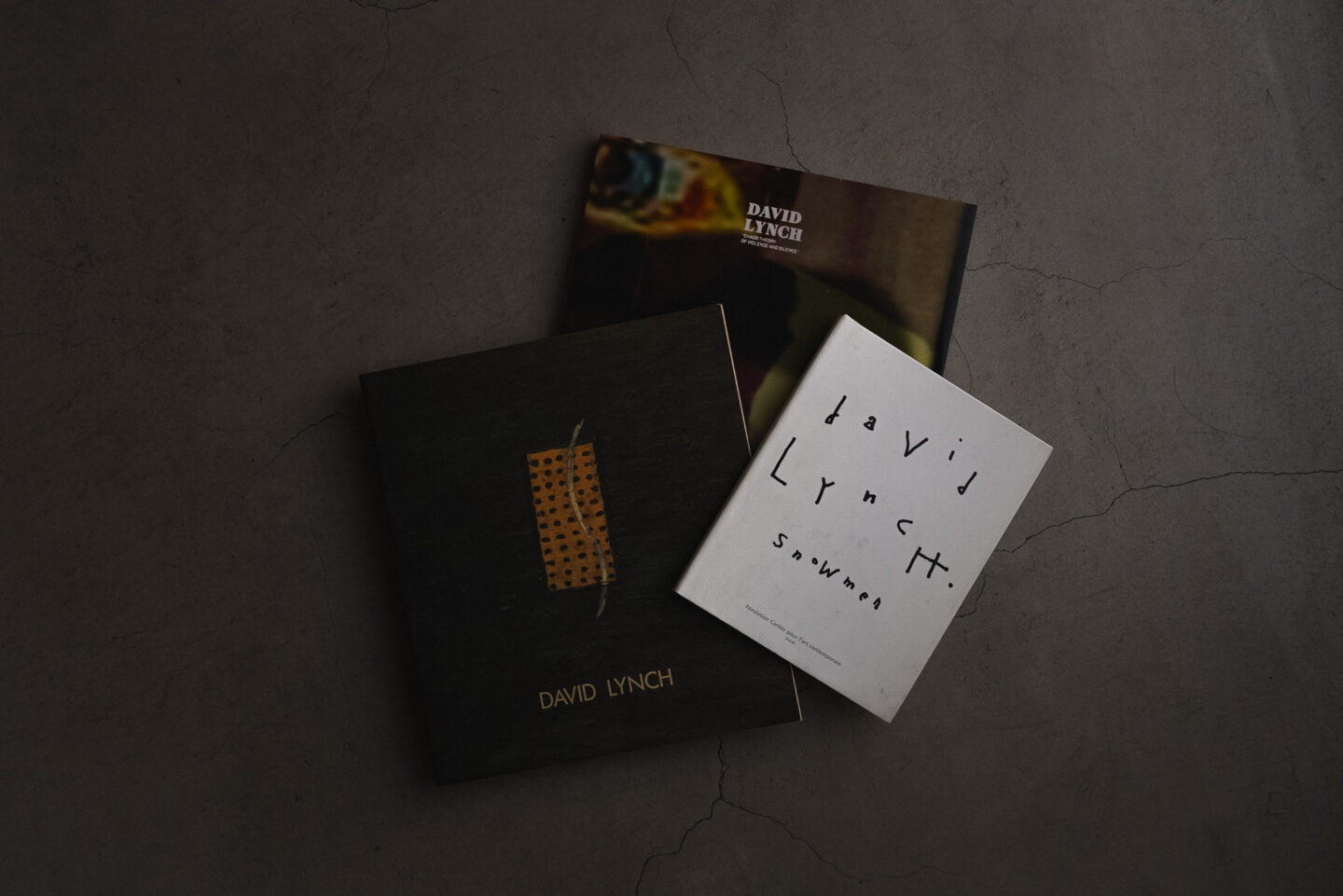
この黒の研究所のコラムのお話をいただいたとき、真っ先に思い浮かんだのはデヴィッド・リンチでした。今回、彼への追悼の気持ちも込めてこのタイミングでコラムにできたことはよかったと思っています。
初めて見た彼の作品は、文芸坐で見た『ブルーベルベット』。時代でいうと、1995年ごろだったと思います。当時は映画を監督で選ぶということが、まだそこまで浸透していなかった時代。ですが、そのころの僕は映画監督の作る世界観みたいなものに惹かれ始めていて。ウディ・アレンやジム・ジャームッシュ、スパイク・リーあたりの、“ニューヨークインディーズ” などアメリカの監督を見ていた中で、デヴィッド・リンチ(以下、リンチ)とか『ツインピークス』とかの名前も聞くようになりました。気になってはいたものの、どこかダウナーな黒いイメージがあって、なかなか手が伸びなかった。でも映画館で上映することを知り、見に行こうと思い立ったんです。そこで『ブルーベルベット』を見て完全に打ちのめされました。
初めてのリンチ作品は、映画館で見られて本当に良かったと思っています。『ブルーベルベット』って、絵に描いたような “アメリカ郊外の幸せな日常” みたいなオープニングシーンからスタートするんです。そこから、庭で水を撒いていたおじさんが急に首をグッと押さえて倒れて、倒れたおじさんにカメラが寄っていくと、芝生の一角に黒い何かがうごめいていて。カメラがどんどんどんどんそこに近づく。寄っていくと黒い虫なのはわかるけど、アリなのかカブトムシなのか、何なのかがわからない。黒い虫は何かに群がっていて、ようやく鮮明に見えそうだと思った瞬間カットされるんです。
で、物語がまたそこから始まるんですけど、オープニングからその暗闇に引きずり込まれた感じがして。真っ暗な映画館でリンチの描く暗闇の中に引きずり込まれるっていうのは、とてつもない体験でしたね。映画館という非日常の空間で見たから、なおさら暗闇の奥の奥まで引きずり込まれたような気がしたんですよね。
『ブルーベルベット』は、暴力とかセックスなど、バイオレンスな要素がある。だから見るのを敬遠してしまったり、見ていて辛かったりします。でもそれ以上にリンチが描こうとしている何かに心が持っていかれる気がするんです。何に心を動かされているのかを言葉で断定できない部分が、きっとリンチ映画の一番の特徴なのではないでしょうか。
その後、『ロストハイウェイ』が劇場公開されたんですが、それはもう難解なストーリーで。『ブルーベルベット』よりも、物語がもっと破綻していながら、闇の部分がもっと色濃く前面に出ていて。それでもやっぱり彼の映画をもっと見たいという気持ちになったんですよね。
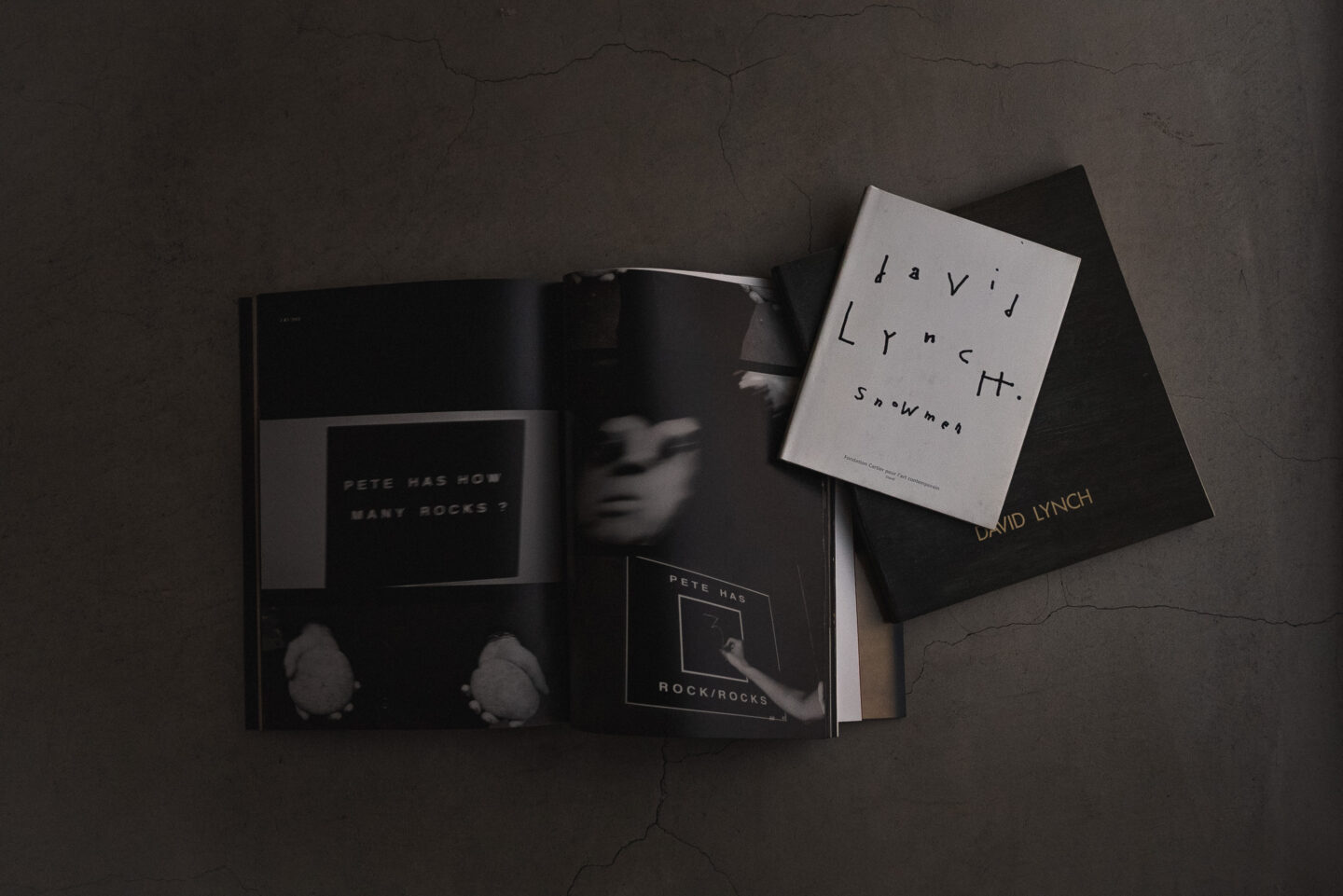
リンチは、日常的に瞑想をしていたと言われています。心を静めて表現に向き合ってきたということなんでしょう。彼のキャリアのはじめは、画家。美大出身で、自分で描いた絵を動かして見たくなったところから、アニメーション制作がスタート。学生時代にアニメを作って評価されて、『イレイザーヘッド』の制作に取りかかった。結果的に『イレイザーヘッド』は完全自主制作で、途中でお金もつきて、もう1回お金を集めて5年かけて完成させて。あれがちょうどこの頃のアメリカンインディーズの流れとうまくマッチして、やばい監督が出てきたと、すごい話題になったんです。そして『ブルーベルベッド』は強烈な世界のまま完成させて、アカデミーの監督賞を受賞しました。
リンチの作品って “わかりづらい” っていうのが枕詞みたいについて回っていますが、それって多分アプローチの仕方が現代アートに近いからだと思うんです。映画だとどうしても「型」があるじゃないですか。物語のある映画を楽しむっていう流れというか。基本的には、枠内で楽しむという安心感を求められるけど、リンチの場合って自分の内側から湧き上がってきたものだけを形にしようとしているからわかりづらいんですよね。イメージの羅列みたいな作品もあって、本人に説明しろと言われてもできるわけないようなものもある。だけど結果的にどの作品も面白い。
『マルホランドドライブ』なんて、前半と後半で辻褄があってないけど、面白いなと感じます。1回見ただけじゃわからなくて、もう1回見るけど、辻褄が合いそうで合わない。気づいたらその世界の虜になっている。その面白さって夢に似てるんですよね。たとえば、夢の中では、僕の中学校のサッカー部の友達と、社会人になってからの知人が、当たり前のように仲良く会話をしている。夢を見てる自分は「あれ? 2人は友達じゃなかったよね」と思う。あの感覚なんですよね。夢だから面白いし、成立する。そんな感じで、リンチの作品って現実かそうじゃないのかわからない世界を行ったり来たりするんです。
それだけ聞くと、わけがわからなくなりそうな気もするんですが(笑)。実は物語はわかりやすく始まって、その中でターニングポイントになる黒い何かが出てくるんです。そこはすごく親切で、『ブルーベルベッド』の場合は、冒頭に出てきた芝生にいる黒い虫。別の作品では、黒い箱が登場することで暗闇の世界へと誘われる。ストーリーは難解ですが、ヒントのようなものはちゃんと存在しています。
リンチ作品では、その “ヒント” に使われる色が黒。リンチは黒を巧みに使いながら、人の恐怖や絶望、ネガティブな潜在意識を描いていたのではと考えています。
人間って弱いから、恐怖やネガティブなものに自分の感情が出会ったとき、蓋をしようとするじゃないですか。でも蓋をして生きてても、心や体の奥底にはうごめいているわけで。それが何かのタイミングで蓋が空いてしまうことがある。リンチ作品で心が持ってかれるっていう感覚は、人間の割と本質的な、恐怖や潜在意識化みたいなところに向き合って作ってるからじゃないかと思っています。しかもすごいのは、「物語」という枠組みは最低限あってエンターテインメントに昇華しているということ。とてもエンタメに昇華できる内容でないことをエンタメにしている。それが彼の才能ですよね。
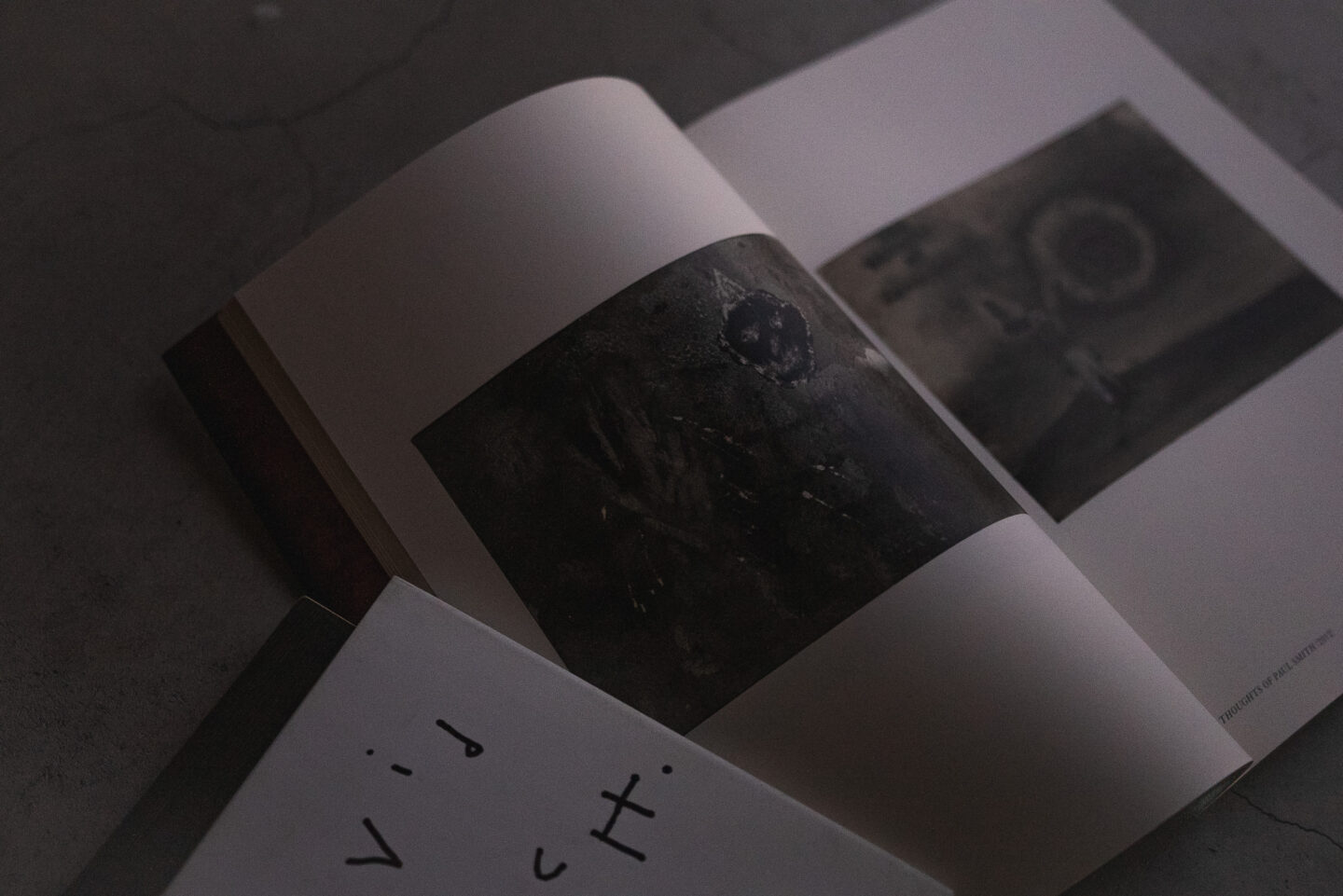
人間の根源的な闇や不安、ネガティブな要素を描き、観客を暗闇の世界へと引きずり込むリンチ作品。論理的な展開よりも、潜在意識や夢のようなイメージを重視し、人の深層心理に迫るような何かを感じられるはず。リンチの表現する闇は、開けてはいけない箱のようでありながら、見なくちゃいけないという気持ちにもなる。鬼才の作る映画、ぜひこれを機に、映画館で見ていただきたいです。
イラスト / 前田ひさえ
有坂塁 (ありさか るい)
『キノ・イグルー』主宰 。中学校の同級生・渡辺順也氏と共に2003年に「キノ・イグルー」を設立。 東京を拠点に全国各地のカフェ、雑貨屋、書店、パン屋、美術館、無人島など、様々な空間で世界各国の映画を上映している。また、映画カウンセリング「あなたのために映画をえらびます」や、毎朝インスタグラムに投稿する「ねおきシネマ」をおこなうなど、自由な発想で映画の楽しさを伝える。“映画パンフレット愛好家”としても活動中。 どんなときでも、 映画の味方です。
HP http://kinoiglu.com
Instagram @kinoiglu

